【老眼鏡の度数】100均と眼鏡店の違いを比較して最適な選び方を解説!

みなさまこんにちは!この記事では「老眼鏡 度数 100均」で検索した読者が抱える不安や疑問を整理しながら、本記事では老眼鏡 度数 100均の基礎と注意点を軸に、100均老眼鏡は目に悪いのか、100均と眼鏡屋の違いを比較、100均の度数は何がある、度数0.5は作れるかの注意、60代の度数目安と距離、100均で視力回復は可能かまでをわかりやすく解説します。
さらに、老眼鏡 度数 100均の選び方として、目的別の度数選びの基本、ダイソーの200円とおしゃれ、セリアやキャンドゥの特徴、口コミとランキングの見方を整理し、最後に老眼鏡 度数 100均のまとめで重要ポイントを総括します。初めての方でも安心して読み進められるよう、専門用語は丁寧に補足しながら解説します。
- この記事でわかること
- 100均老眼鏡と眼鏡店の老眼鏡の違いと選び分け
- 目的別の度数選びの基本手順と試し方
- 年代と作業距離の目安から度数を推定する考え方
- 口コミやランキングの読み解き方と注意点
100均の老眼鏡の度数について基礎と注意点
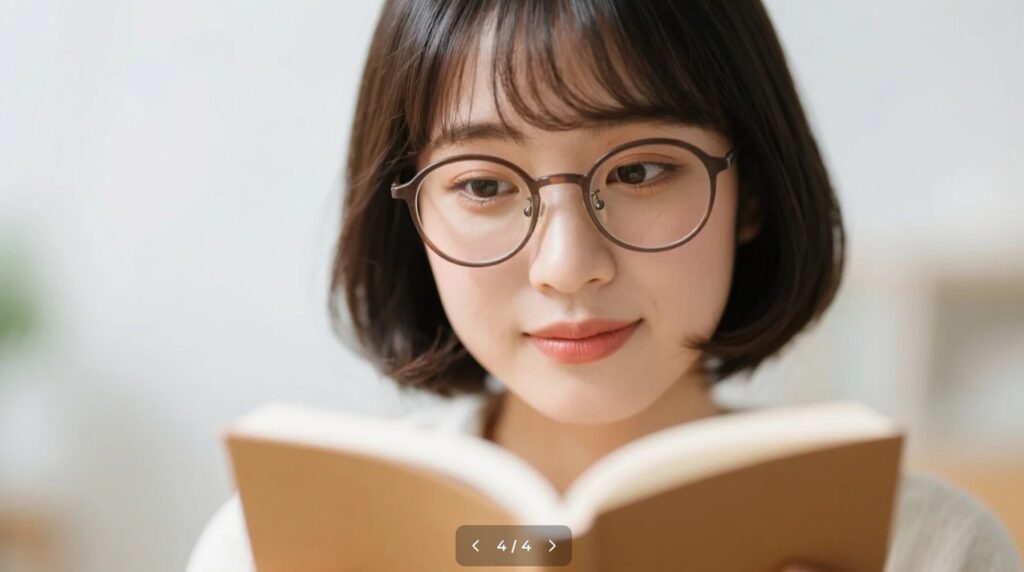
100均老眼鏡は目に悪いのか
100均で販売されている老眼鏡は、短時間の使用や急な場面での「置きメガネ」として利用する分には、多くの専門家の見解によると大きな問題はないとされています。しかし、これらの老眼鏡は既製品であり、左右の度数が同じであること、さらに瞳孔間距離(PD:Pupillary Distance)が平均値で設計されていることが特徴です。そのため、一人ひとりの視力や目の構造に合わせて作られていない点には注意が必要です。
特に、左右の度数差が大きい方や乱視を持つ方、平均的な瞳孔間距離から外れている方の場合には、違和感を覚えるリスクが高まります。例えば、焦点を切り替えた際に視界が揺れてふらつきを感じたり、頭痛や肩こりが起こったりすることがあります。こうした症状は、目と脳が無理にバランスを取ろうとすることで引き起こされるとされています。
違和感の具体例としては以下のようなものが挙げられます。
- 本を読んでいると視界が揺れて安定しない
- 視線を近くから遠くに移したときにくらくらする
- こめかみや後頭部に重さを感じる
- 長時間使用すると肩や首に負担を感じる
このような症状が現れた場合は、使用を中止し、眼科での精密な検査や眼鏡専門店での相談を行うことが推奨されます。また、日本眼科医会も「既製老眼鏡は一時的な使用には適しているが、長期的には個別に調整した眼鏡を使用することが望ましい」としています(出典:日本眼科医会 https://www.gankaikai.or.jp/
さらに、100均老眼鏡はフレームやレンズの品質に個体差があることも指摘されています。レンズのコーティングが薄いために傷がつきやすかったり、歪みがあるレンズに当たってしまう可能性も否定できません。そのため、長時間の連続使用は避け、外出時の予備や緊急用途にとどめることが安全だと考えられます。
要するに、100均老眼鏡は「安価で手軽に入手できる」というメリットがある一方で、個々の目に最適化されていないため、長期使用や常用には適していません。短時間の使用であれば便利ですが、目の健康を守るためには、必ず眼科での診断や専門店でのフィッティングを受けることが鍵となります。
100均と眼鏡屋の違いを比較

既製品とオーダーメイドでは、製品思想が異なります。費用と即時性に優れる一方で、合わせ込みの精度は眼鏡店に軍配が上がります。
| 項目 | 100均既製老眼鏡 | 眼鏡店の老眼鏡 |
|---|---|---|
| 度数設計 | 左右同度数が基本 | 片眼ずつ測定し個別最適 |
| 乱視補正 | なし | あり |
| 瞳孔間距離 | 平均値で固定 | 個別に合わせる |
| フィッティング | 調整不可が多い | 調整可 |
| 使用推奨時間 | 短時間・予備用途向き | 長時間使用に向く |
| 価格帯 | 低価格 | 中〜高価格 |
| 目的適合 | 限定的 | 用途別設計が豊富 |
以上の点を踏まえると、読書やメニュー確認など短時間の用途であれば既製品、仕事や長時間の作業には眼鏡店の合わせた老眼鏡が適します。
100均で売っている老眼鏡の度数は何がある?

100円ショップで販売されている老眼鏡は、多くの場合プラス1.0からプラス3.5までの範囲で0.5刻みの度数展開が一般的です。つまり、+1.0、+1.5、+2.0、+2.5、+3.0、+3.5といった度数が店頭でよく見られます。これは大量生産に適した標準化された仕様であり、個々の視力や瞳孔間距離に合わせて作られたものではありません。
度数の特徴と距離の目安
度数によってピントが合う距離は異なり、用途に応じて選び方が変わります。
- +1.0〜+1.5:50〜70cm程度(パソコンや少し離れた書類向き)
- +2.0:40〜50cm程度(デスクワークや雑誌に適する)
- +2.5:30〜40cm程度(文庫本やスマートフォンに適する)
- +3.0〜+3.5:25〜30cm程度(細かい手元作業向け)
このように、強い度数ほど焦点距離が近くなるため、自分がよく使う距離に合わせて選ぶ必要があります。
選び方のポイント
売り場では実際に試し掛けが可能な場合が多く、新聞やスマートフォンの文字などを基準に、以下の点を意識して選ぶことが勧められます。
- 読める選択肢の中で最も弱い度数を選ぶ
- 長時間使用を前提とせず、短時間利用を想定する
- 強すぎる度数は頭痛や吐き気の原因になる可能性がある
また、店舗や時期によっては+4.0まで置いている場合もあれば、+1.0〜+3.0までしか展開していないこともあります。仕入れ状況が異なるため、必要な度数があるかどうかを確認してから購入すると安心です。
度数0.5は簡単に作れるか?

100均の既製老眼鏡では、+0.5や+0.75といった弱い度数の商品はほとんど流通していません。これは需要の多い中度〜高めの度数にラインアップを絞ることで、生産効率を高めているためと考えられます。
弱い度数が必要なケース
老眼の初期段階や、まだ軽度の補助があれば十分な方にとっては+0.5程度の弱い度数が適していることがあります。具体的には以下のようなケースです。
- 40代前半〜50代前半で近くが少し見づらくなってきた人
- 長時間のデスクワークで軽い補助が欲しい人
- 強い度数では視野が狭くなり疲れやすい人
対応方法
弱い度数を必要とする場合は、以下の手段が現実的です。
- 眼鏡店で+0.5や+0.75を処方・作製してもらう
- 眼科で検査を受け、生活に合う度数を確認する
- 乱視や瞳孔間距離の調整も含め、オーダーメイドで作る
特に老眼初期は度数の過剰矯正がかえって目の負担になることがあるため、無理に強い度数を選ばないことが推奨されます。
厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、加齢に伴う視機能の低下は50代以降で急激に増える傾向が報告されています(出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html
そのため、初期の段階では特に精密な検査を受け、自分に合う弱い度数を正しく処方してもらうことが、快適な生活につながるといえます。
60代の度数目安と距離について

年齢はあくまで目安ですが、加齢に伴い近方調節力が低下するため、必要度数は高くなる傾向があります。以下は読書距離の目安とされる情報を整理したものです。
| 想定距離の目安 | よく使うシーン | 必要度数の目安とされる範囲 |
|---|---|---|
| 約60〜70cm | ディスプレイ作業 | プラス1.0〜プラス1.5 |
| 約40〜50cm | 書類整理・タブレット | プラス1.5〜プラス2.0 |
| 約30〜40cm | 読書・スマホ | プラス2.0〜プラス2.5 |
| 約25〜30cm | 細かい手元作業 | プラス2.5〜プラス3.0 |
60代では読書距離が30〜40cmの場合、プラス2.0〜プラス2.5が候補になるという説明が多く見られます。ただし個人差が大きいため、眼科検査や店頭での見え方確認が欠かせません。
100均の老眼鏡で視力回復は可能か

近年、一部の雑誌や健康関連メディアでは「既製老眼鏡を使ったトレーニングで視力が改善する」といった方法が紹介されることがあります。例えば、度数の異なる老眼鏡を掛け替えてピント調節を刺激したり、短時間の使用で眼の筋肉を意図的に働かせるといった手法です。しかし、こうした方法については科学的根拠が十分に確立されているわけではなく、医療的な合意が得られているわけではありません。
視力回復と老眼の関係
老眼は、水晶体の弾力性が加齢に伴って低下し、ピント調節力が衰えることで起こります。つまり「筋肉を鍛えれば治る」性質のものではなく、加齢現象として誰にでも起こり得る変化です。視力回復トレーニングが紹介される背景には「毛様体筋(ピントを合わせる筋肉)のリラックスや一時的な疲労軽減」がありますが、恒常的な視力改善が得られることを保証するものではありません。
よく取り上げられる効果と限界
視力回復を目的にした老眼鏡活用法では、以下のような効果が期待されるとされています。
- 長時間のパソコン作業や読書による眼精疲労を軽減する
- ピント調節筋をリラックスさせることで、目の緊張を和らげる
- 一時的に近くの文字が見やすくなり、作業効率が上がる
ただし、これらは「疲労軽減」や「リラックス」といった効果であり、医学的に老眼そのものを根本的に改善するものではありません。厚生労働省や日本眼科学会など公的機関や学会の情報においても「老眼を完全に回復させる治療法は現時点で確立されていない」と説明されています。(出典:日本眼科学会 https://www.nichigan.or.jp/)
注意すべき点
- 安価な既製老眼鏡を長時間使用し続けると、左右差や乱視に対応していないため、かえって疲労や頭痛を悪化させる場合があります。
- 度数が強すぎるレンズを「トレーニング目的」で使うと、視界が歪んだり、吐き気を感じることもあります。
- 視力の低下や焦点の合わせにくさが続く場合は、必ず眼科を受診して原因を特定することが大切です。
まとめ
100均の老眼鏡は手軽に試せる点が魅力ですが、「視力回復を目的に使う」のではなく「疲労軽減や予備用」として位置づけるのが現実的です。恒常的な改善を求める場合には、眼科での診察や専門的な治療を受けることが望ましく、安易に自己流のトレーニングだけに頼ることは避けたほうが安心です。
100均老眼鏡の度数の選び方

目的別の度数選びの基本
老眼鏡は「どの距離を、どのくらいの時間、どんな姿勢で見るか」によって最適解が変わります。まずは用途を具体化し、作業距離を測ったうえで、読める度数の中から最も弱いものを選ぶ流れが実用的です。強すぎる度数は視野が狭くなり、姿勢や目の動きに制約が出やすくなるため避けたほうが快適に使えます。
3ステップで決める度数選び
- 用途を洗い出す
読書、スマホ、パソコン、書類整理、裁縫、料理のレシピ確認、会議中のメモなど、よく使う順に挙げます。掛け外しの頻度を減らしたいのか、最優先の1シーンに最適化したいのかも決めておきます。 - 作業距離を測る
メジャーで「目から対象物まで」の距離を測ります。読書は30〜40cm、ノートPCは40〜60cm、デスクトップやデュアルモニターは50〜70cmになることが多いです。普段の姿勢(椅子の高さ、モニター位置、照明)で測るのがコツです。 - 店頭で最弱を選ぶ
測った距離で対象を見ながら、読める度数の中で最も弱いものを選びます。1〜2分連続で見て、目や肩に力みが出ないか、遠くへ視線を戻したときの違和感が強くないかを確認します。
距離別のおおよその目安
| 主な用途 | 目からの距離の目安 | 試し始めの度数の目安(最弱から) |
|---|---|---|
| デュアルモニター作業 | 60〜70cm | +1.0前後 |
| ノートPC・タブレット | 45〜60cm | +1.0〜+1.5 |
| 書類整理・雑誌 | 40〜50cm | +1.5〜+2.0 |
| 文庫本・スマホ | 30〜40cm | +2.0〜+2.5 |
| 細かい手作業 | 25〜30cm | +2.5〜+3.0 |
上表は一般的な目安であり、個人差があります。まずは弱めから試し、必要に応じて0.5刻みで調整すると、楽に使えるポイントを見つけやすくなります。
強すぎ・弱すぎを見分ける簡易チェック
- 強すぎのサイン
近くはくっきりだが少し顔を起こすと急にぼやける、視野の端が歪んで感じる、遠くにピントを戻しづらい、肩や首に力が入りやすい - 弱すぎのサイン
文字の黒が薄くにじむ、無意識に顔を近づける、眉間にしわが寄る、数分で目のしょぼつきが出る
違和感が出たらその度数は避け、読める中でより弱いもの(強すぎのとき)または0.5段階強いもの(弱すぎのとき)に切り替えて再確認します。
用途が複数ある場合の考え方
- 仕事中心で掛け外しを減らしたい
デスクワーク主体なら、作業距離に最適化した単焦点を1本用意し、会議スペースや社内移動が多いなら中近(室内用)や遠近といった目的別設計の検討が役立ちます。既製老眼鏡は単焦点が基本のため、広い範囲を見渡したいときは眼鏡店での相談が近道です。 - シーン別に最適を使い分けたい
PC用(たとえば+1.5)と読書用(たとえば+2.0)を分けて持つと姿勢が安定しやすく、疲労の蓄積を抑えられることがあります。ケースやフレーム色で用途をラベリングしておくと取り違えを防げます。
近視・乱視・左右差がある場合
100均の既製老眼鏡は「左右同度数・乱視補正なし・平均的な瞳孔間距離」で作られています。次の条件に当てはまる場合は、既製品で違和感が出やすくなります。
- 乱視がある、左右の度数差が大きい
- メガネやコンタクトで日常的に矯正している
- 近視で、裸眼だと手元は見えるが遠くが見えにくい
特に近視の人は、裸眼で手元が見やすいことが多く、上乗せの度数が不要または少量で済む場合があります。一方、常用のメガネやコンタクトを装用したまま手元を見ると、追加のプラス度数が必要になることがあります。こうした条件では、眼鏡店での度数測定とフィッティングを前提に選ぶほうが快適です。
店頭での試し方のコツ
- いつも読む文字サイズと紙質(新聞、文庫、スマホ)で確認する
- 普段の姿勢に近い高さで、1〜2分連続で見続けてみる
- 見終わったら遠くへ視線を戻し、違和感やふらつきがないかを確かめる
- 照明の明るさも影響するため、暗い環境用には少し強めが楽になる場合がある
中近・遠近など目的別設計が合うケース
- デスクトップと会議資料、室内の人の動きの両方に素早く対応したい
- 事務作業で上下左右へ視線移動が多い、立ち歩きが混じる
- 一日を通して掛けっぱなしに近い運用をしたい
このようなときは、単焦点の既製老眼鏡では視野や焦点移動の自由度が足りないことがあります。室内用(中近)や遠近など、多焦点設計のレンズは眼鏡店での個別設計が前提になるため、用途や距離のヒアリングを受けながら選ぶのが効率的です。
以上のポイントを踏まえると、まずは用途と距離を明確にし、店頭では最弱から段階的に試すことが、無理のない度数選びにつながります。違和感が取れない、複数用途で困る、近視・乱視・左右差があるといった場合は、眼鏡店での測定とフィッティングに切り替えると、快適性が大きく向上します。
ダイソーの200円老眼鏡とおしゃれについて

ダイソーでは、標準的な110円(税込)の既製老眼鏡に加え、200円や300円といった価格帯の商品も展開されています。これらは単に価格が高いだけでなく、フレームの素材やデザイン性、かけ心地に配慮した仕様が多いことが特徴です。例えば、軽量樹脂や金属パーツを取り入れたモデル、柔らかいテンプル(つる)でフィット感を高めたモデルなどがあり、より快適に使えるよう工夫されています。
デザイン面では、以下のように幅広いバリエーションが見られます。
- ボストン型やオーバル型など、顔立ちを選ばないクラシックデザイン
- 大きめのビッグフレームで、視野が広く快適なタイプ
- 細身のフレームやカラー展開が豊富で、おしゃれの一部として楽しめるタイプ
これらは、ファッション性を重視する層や、外出時にも自然に使いたい層から人気を集めています。鼻メガネのように掛け位置を工夫することで、手元作業から少し遠くを見る動作まで切り替えやすくなるため、使い勝手の良さも大きなポイントです。
さらに、一部の商品にはブルーライトカット機能が表示されています。ブルーライトカット率は商品ごとに異なり、体感効果には個人差が大きいとされています。特にパソコンやスマートフォンを長時間使用する方にとっては便利ですが、数値はあくまでメーカー仕様に基づくものであり、表示が必ずしも医療的効果を保証するものではありません。そのため、実際に店舗で掛けて見え方を確認し、長時間使用に適しているかどうかを自分で判断することが重要です。
セリアやキャンドゥにある老眼鏡の特徴

セリアでは、比較的強めの度数(+3.0や+3.5)がラインアップされていることがあると報告されています。特に高齢層の利用者にとっては、強度数の選択肢が広がる点が大きなメリットです。また、ケース付きモデルやフレームレスの軽量タイプなど、携行性や快適さに配慮した商品も多く、日常使いに適しています。カラーバリエーションも豊富で、見た目にこだわる方に選ばれる傾向があります。
一方、キャンドゥはベーシックなデザインが中心で、落ち着いた色味や軽量設計が特徴です。持ち運びに便利なケース付きモデルが多く、家の中だけでなく外出用の予備として複数購入するケースも見られます。価格が抑えられているため、自宅や職場、バッグなどに複数配置しやすい点も魅力です。
ただし、セリア・キャンドゥともに注意すべきは「店舗ごとの品ぞろえの違い」です。チェーン全体で統一されているわけではなく、店の規模や仕入れ状況によって取り扱い度数やカラー展開が異なります。そのため、次のような工夫が役立ちます。
- 実際に売り場で試し掛けを行い、自分の視力や用途に合うかを確認する
- 同じチェーンでも複数の店舗を回ることで、より幅広い選択肢を探せる
- 定期的に売り場をチェックし、欲しい度数やデザインが入荷されていないか確認する
こうした下調べをしてから購入することで、度数やデザイン選びの失敗を減らすことができます。
口コミとランキングの見方

インターネットや商品レビューサイトでは、100均老眼鏡に関する口コミやランキングが数多く掲載されています。しかし、それらの評価を鵜呑みにするのは適切ではありません。理由は、老眼鏡の見え方や快適性は以下のような個人差に大きく左右されるためです。
- 使用者の度数や瞳孔間距離の違い
- 乱視の有無や左右の視力差
- 使用シーン(読書中心か、PC作業中心か)
- かけ心地やデザインへの好み
ランキングも同様に、在庫状況や季節要因で順位が変動することがあり、必ずしも「品質の高さ」を直接的に反映しているわけではありません。したがって、口コミやランキングはあくまで「参考情報」として読み解くことが大切です。
判断材料として有効なのは、次のような要素です。
- 店頭で試し掛けできるかどうか
- フレームの調整余地やフィット感
- 重量や鼻パッドの形状
- ケースや付属品の有無
- レンズの傷つきやすさ、ヒンジ部分の耐久性
特に耐久性については「価格相応」との声が多く、レンズが傷つきやすい、フレームが緩みやすいといった指摘が散見されます。そのため、100均老眼鏡は「予備用」「短時間利用用」として位置づけ、本格的に長時間使う場合は眼鏡店での作製を検討するのが現実的です。
こうした視点を持つことで、口コミやランキングに振り回されず、自分にとって最適な老眼鏡を選ぶ基準が明確になります。
100均一老眼鏡の度数まとめ

- 100均老眼鏡は短時間用途なら活用しやすい
- 長時間用途や仕事用は眼鏡店の合わせ込みが有利
- 度数は読める中で最も弱い選択が無難
- 100均の一般的な度数はプラス1.0〜3.5
- プラス0.5は眼鏡店での作製が現実的
- 60代は30〜40cmでプラス2.0〜2.5が候補
- 左右差や乱視がある場合は既製品が不利
- かけ心地と視野の広さは店舗で確認が必要
- ブルーライトカット表示は体感に個人差がある
- ダイソーは価格帯やデザインの幅が広がる傾向
- セリアやキャンドゥは強め度数や携行性が魅力
- 口コミやランキングは試し掛け前提で参考にする
- 視力回復をうたう手法はエビデンスに限界がある
- 違和感や頭痛が出たら使用を中止して相談する
- 老眼鏡 度数 100均は目的と距離で賢く選ぶ


